5月の時候の挨拶|上旬・中旬・下旬別ですぐ使える例文集
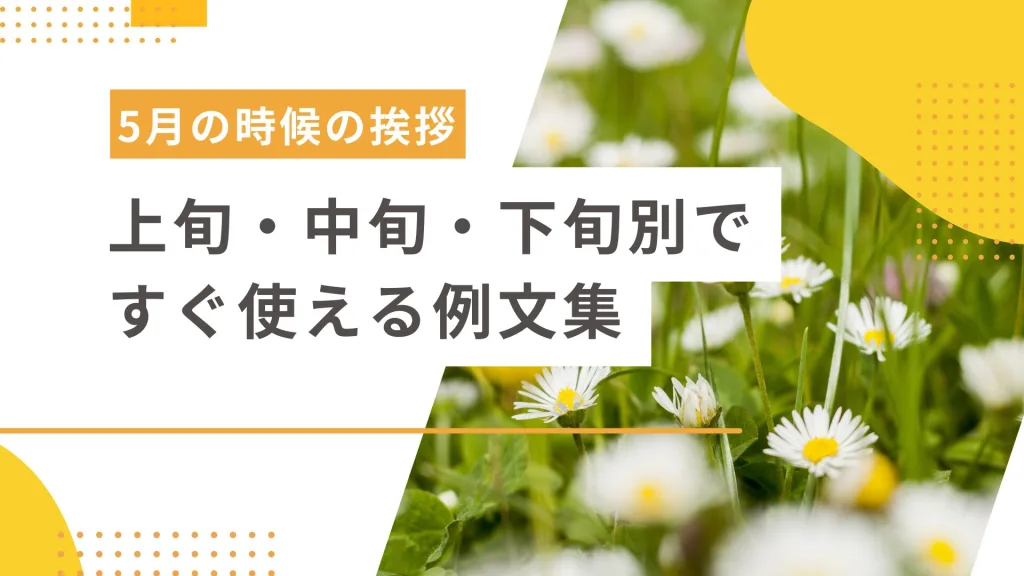
春の穏やかな空気から初夏へと移り変わる5月は、新緑がまぶしく、爽やかな風が心地よい季節です。手紙やメールの冒頭に添える「時候の挨拶」も、この季節ならではの言葉を選びたいもの。この記事では、5月にぴったりの時候の挨拶を上旬・中旬・下旬に分けて紹介し、さらにビジネスやプライベートなどシーン別の文例も掲載。すぐに使える例文集として、皆さんのご挨拶文作成をサポートします。
5月の時候の挨拶とは?
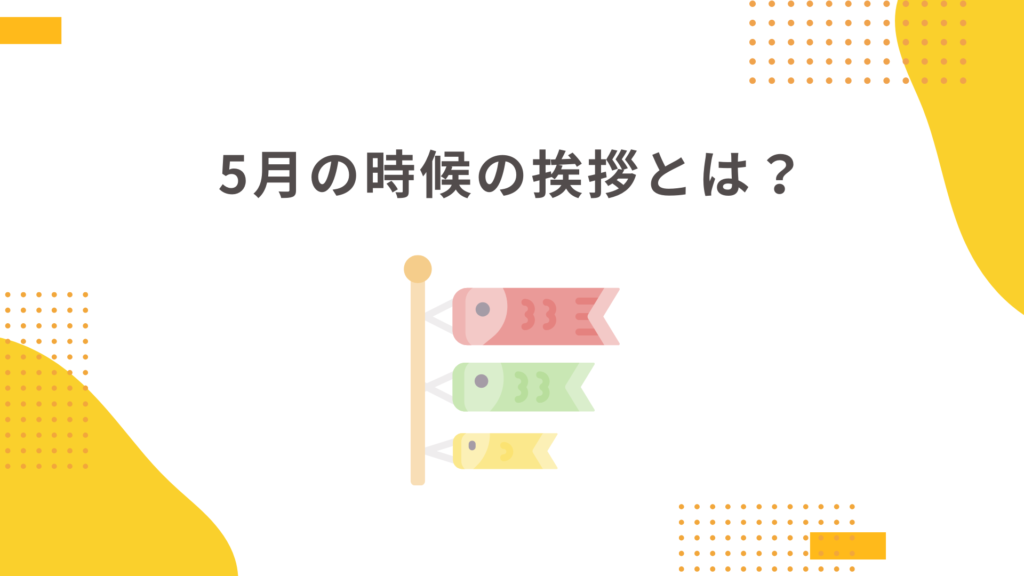
時候の挨拶の基本と役割
時候の挨拶は、日本の伝統的な文章作法のひとつで、季節の自然や天候に触れて、文章の冒頭に添えることで礼儀を示します。相手への敬意や心配りを表現する役割があり、ビジネス文書やお礼状、季節の挨拶状などでよく使われます。
ビジネスでは漢語調でややフォーマルな表現、個人間では自然体で口語的な表現を選ぶと、シーンに合った印象の良い文章になります。
5月の特徴と季節感
5月は、新緑が生い茂り、爽やかな風が吹き抜ける初夏の入り口。ゴールデンウィークをはじめ、端午の節句や母の日など行事が多く、日差しも一層明るく感じられます。自然界が活気づくこの季節は、挨拶文にも「生命力」や「爽やかさ」といったキーワードがよく合います。
5月の時候の挨拶を時期別に解説
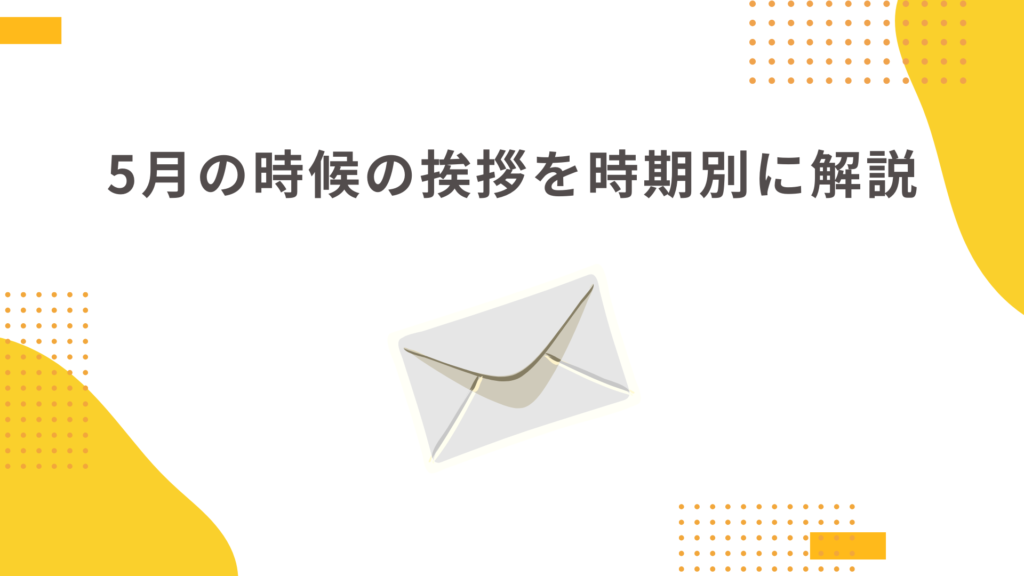
5月上旬の挨拶例と季語
5月上旬はゴールデンウィークの真っただ中。新緑や若葉など春から初夏への移ろいを感じさせる季語がよく使われます。
季語の例:新緑の候、若葉の候、薫風の候
例文(漢語調)
- 新緑の候、貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
- 若葉の候、皆様におかれましてはご清栄のことと存じます。
- 薫風の候、時下ますますご隆盛のこととお喜び申し上げます。
例文(口語調)
- 若葉がまぶしく感じられる季節となりましたが、お元気でお過ごしでしょうか。
- 爽やかな風に夏の気配を感じる今日この頃、いかがお過ごしですか?
- 新緑のまぶしい季節となりました。ご家族の皆様もお健やかでいらっしゃいますか。
5月中旬の挨拶例と季語
5月中旬は暦の上で「立夏」を迎え、日中の気温も上がってきます。初夏らしい爽やかな季語や、成長を感じさせる言葉がふさわしい時期です。
季語の例:立夏の候、初夏の候、新茶の候
文例(漢語調)
- 立夏の候、貴社いよいよご隆盛のこととお喜び申し上げます。
- 初夏の候、皆様にはご壮健のこととお慶び申し上げます。
- 新茶の候、貴社ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。
文例(口語調)
- 木々の緑が深まり、初夏の風が心地よく感じられる季節となりました。
- 日差しに夏の気配が感じられる今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。
- 青空に映える新緑がまぶしい季節ですね。皆様のご健康をお祈りしております。
5月下旬の挨拶例と季語
5月下旬は「小満」の頃。陽射しが強くなり、夏が目前に迫ってくる時期です。暑さを思わせる語句や、体調への気遣いを表現に取り入れましょう。
季語の例:小満の候、向暑の候、軽暑の候
文例(漢語調)
- 小満の候、皆様におかれましてはご健勝のことと拝察いたします。
- 向暑の候、貴社ますますご清栄の段、お慶び申し上げます。
- 軽暑の候、時下ますますご発展のこととお慶び申し上げます。
文例(口語調)
- 夏の気配を感じるようになってまいりましたが、体調など崩されていませんか?
- 木々の葉が濃くなり、日差しも一層強く感じられるようになってきました。
- 初夏の暑さが近づいておりますが、変わらずお元気でお過ごしのことと存じます。
シーン別の挨拶文例
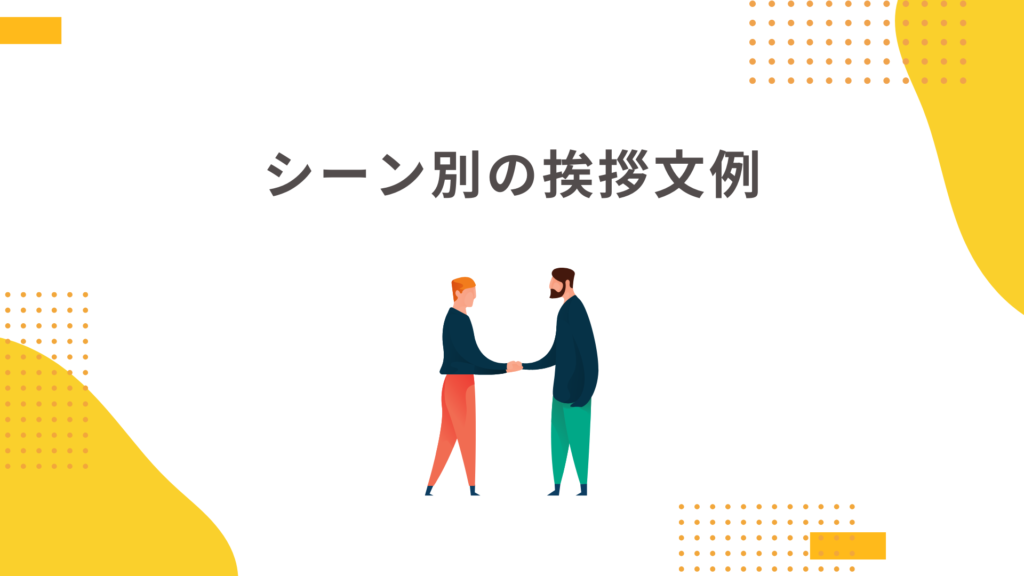
ビジネスシーンでの挨拶例
ビジネス文書では、漢語調を用いた丁寧な表現が基本です。冒頭に時候の挨拶を置き、その後に感謝や用件を簡潔に続けます。
- 薫風の候、貴社におかれましてはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
- 若葉の候、平素より格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
- 立夏の候、貴社のご発展と皆様のご健勝を心よりお祈り申し上げます。
プライベートでの挨拶例
親しい相手に送る手紙やメールでは、自然な言葉遣いで温かみのある表現が喜ばれます。
- 風薫る季節となりましたが、お元気でいらっしゃいますか?
- 新緑の美しい季節ですね。そちらはいかがですか?
- 爽やかな初夏の陽気が続いていますが、ご家族皆様お変わりありませんか。
結びの言葉の選び方
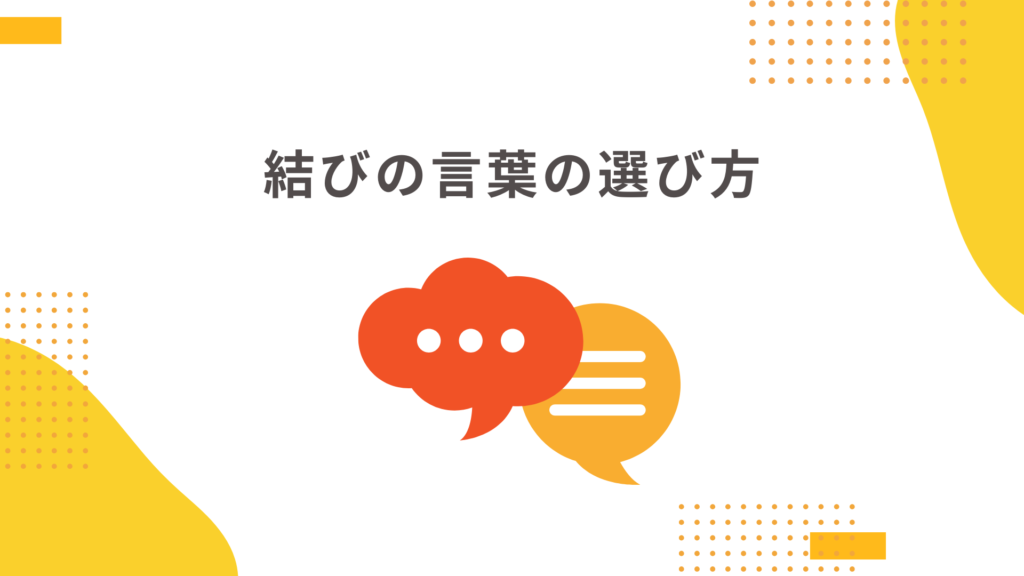
時候の挨拶の締めくくりに欠かせない「結びの言葉」。これは単なる終わりの表現ではなく、相手を思いやる気持ちや、文全体の余韻を残すための大切な一文です。特に5月は季節の変わり目であるため、体調や健康を気遣う言葉や、今後の関係性を円滑にする丁寧な表現が求められます。ここでは、目的や相手との関係性に応じた3タイプの結びの例文をご紹介します。
健康を気遣う結びの例
5月は気温の変動が大きく、体調を崩しやすい時期でもあります。そのため、相手の健康を気遣う一言を添えることで、心のこもった印象を与えることができます。特に年配の方や体調に不安のある方への配慮として効果的です。
- 季節の変わり目ですので、どうかご自愛くださいませ。
- 朝晩と日中の寒暖差がありますので、どうぞお体を大切に。
- 初夏の陽気に体調を崩されませんよう、くれぐれもご注意ください。
ビジネスに適した丁寧な結び
ビジネス文書の締めくくりには、礼節を重んじたフォーマルな表現が求められます。相手への敬意を忘れず、信頼関係をより深めるような文面を意識しましょう。会社宛、目上の方、取引先などでの使用に最適です。
- 今後とも変わらぬご厚誼を賜りますようお願い申し上げます。
- 貴社の一層のご繁栄を心よりお祈り申し上げます。
- 引き続きご指導・ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。
親しい相手向けのやさしい表現
親しい友人や家族、長年の付き合いのある相手には、やわらかく、親しみのある言葉で締めくくると、より温かな印象になります。ビジネスでないからこそ、感情をのせた言い回しが喜ばれるでしょう。
- お互い元気にこの季節を楽しみましょうね。
- また近いうちにお会いできる日を楽しみにしています。
- ご家族の皆様にもどうぞよろしくお伝えください。
5月に使える代表的な季語一覧
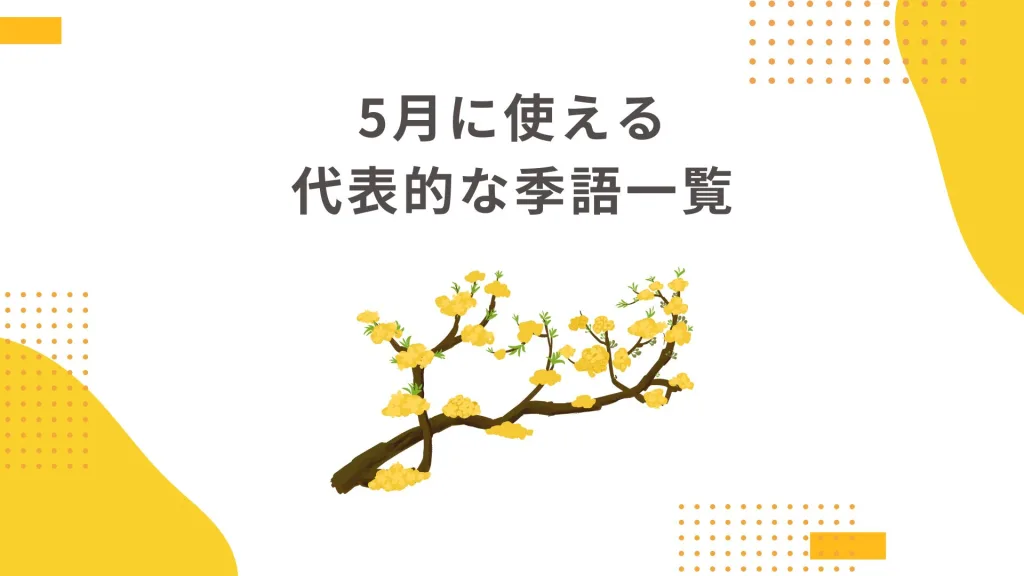
5月は四季の中でも特に自然の変化が美しく表れる月です。そのため、季語も多彩で、自然・気候・行事にまつわるさまざまな言葉が活用できます。文中に季語を自然に取り入れることで、文章に深みと季節感が加わります。
二十四節気に基づく季語(立夏・小満)
二十四節気とは、1年を24等分して季節の移ろいを細やかに表した暦の区切りです。これを用いた季語は格式高く、特にビジネス文書やかしこまった挨拶状に適しています。
立夏(りっか)(5月5日頃)
「夏が立つ」と書く通り、暦の上で夏の始まりを意味します。「立夏の候」は、5月中旬まで使える初夏の定番表現です。
小満(しょうまん)(5月21日頃)
草木や作物が成長して満ち始める時期。「小満の候」は5月下旬にふさわしい季語で、自然の力強さを表現できます。
自然を表す季語(新緑・風薫るなど)
5月は自然が最も美しい季節の一つ。若葉や清風など、視覚・聴覚・触覚に訴える季語を使うと、臨場感のある文章になります。
青葉、若葉、緑風
それぞれ若々しさや生命力を感じさせる語句。清潔感や爽やかさが表現され、個人宛の挨拶でも使いやすいです。
新緑
みずみずしい若葉の色。春から夏へ移り変わる瞬間の美しさを表現する代表的な季語です。
薫風(くんぷう)
香り立つような爽やかな風を指す言葉で、「薫風の候」は非常に品があり、挨拶文でも人気のある季語です。
行事を取り入れた季語(端午の節句・母の日)
5月は日本の伝統行事が多く、それに関連する言葉を使うことで、よりパーソナルで印象的な文章に仕上がります。
母の日(5月第2日曜日)
「感謝」や「ぬくもり」をテーマにした挨拶文が合います。義母や年長の知人に対して使うと好印象です。
端午の節句(5月5日)
男の子の健やかな成長を願う日。「端午の節句にちなんで~」という書き出しで、季節の話題を自然に導入できます。
鯉のぼり
元気に泳ぐ姿を描写することで、文章に動きと明るさを加えることができます。
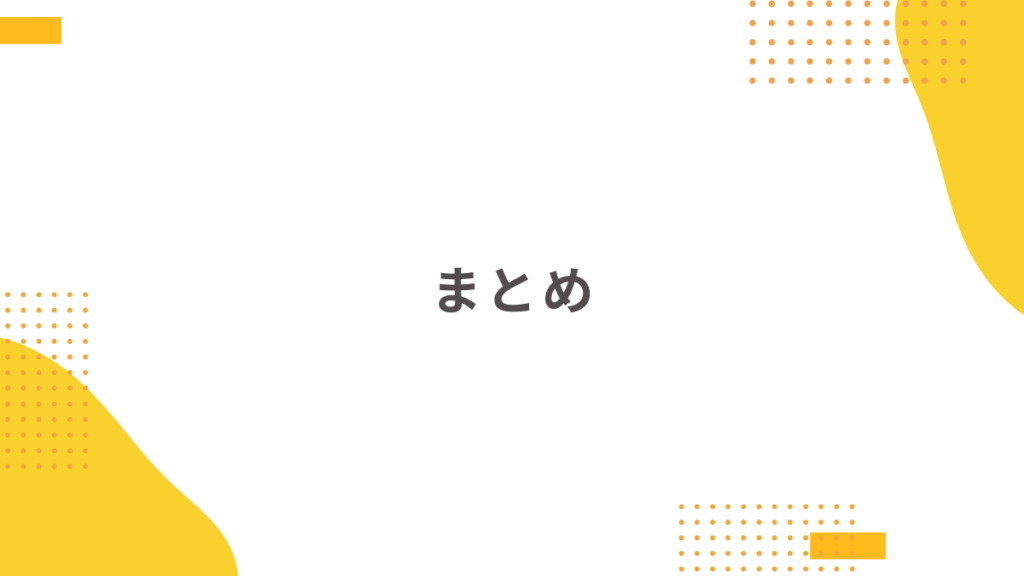
まとめ
5月は、自然の美しさと季節の移り変わりを感じやすい月です。その魅力を表現した時候の挨拶は、読み手の心を和ませる大切な要素。時期別の季語や文例をうまく活用し、形式的ながらも心のこもった言葉を届けましょう。この記事を参考に、ぜひ自分らしい挨拶文を作成してみてください。
