謝礼金に税金はかかる?税金・勘定科目・申告方法まとめ
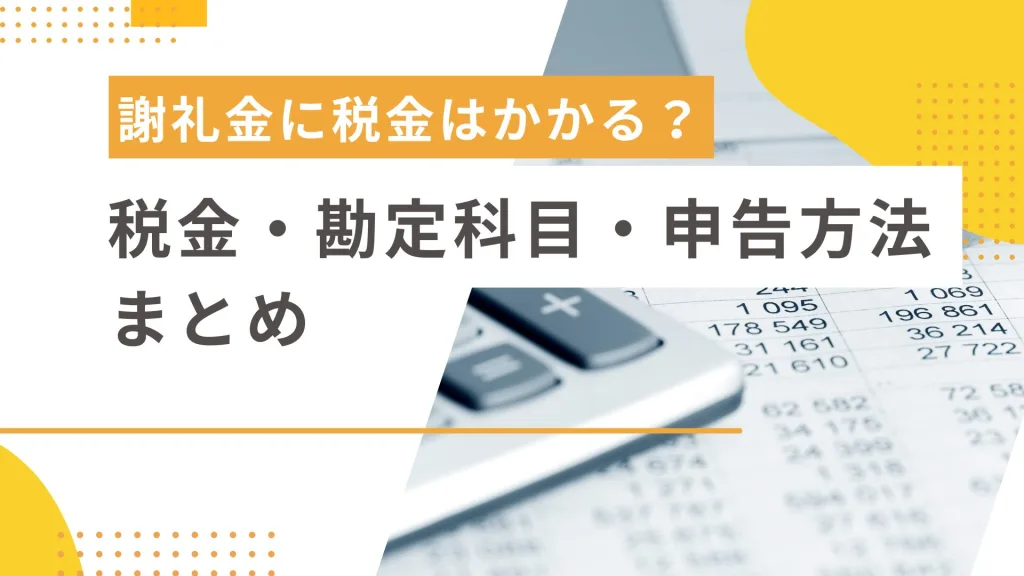
「謝礼金を受け取ったけれど、これって税金はかかるの?」
講演会の謝礼やアンケートの謝礼など、思いがけず受け取った謝礼金。実はその謝礼金、所得として扱われる可能性があり、税金がかかるケースがあります。また、正しい税務処理や確定申告を行わないと、後から税務署から指摘されてしまう可能性も。
本記事では、謝礼金にかかる税金の種類や申告方法、源泉徴収の有無、勘定科目の選び方などをわかりやすく解説します。
謝礼金とは?基本を理解しよう
謝礼金の定義と特徴
謝礼金とは、特定の契約や業務委託による報酬ではなく、受け取った人の行為や協力に対して感謝の意を表して支払われる金銭や物品のことを指します。謝礼金は、企業や団体、個人から「協力してくれたことへのお礼」として支払われるケースが多く、法的な義務や労働契約が伴わないのが特徴です。
謝礼金が発生する具体例
- 講演やセミナーの謝礼
- イベント協力や出演の謝礼
- アンケートや調査への協力に対する謝礼
- 取材協力や執筆依頼の謝礼
- 講演やセミナーの謝礼
企業や団体が講演会を開催し、その講演を担当した個人に対して支払われるケース。講演の依頼に契約が伴わず、感謝の意味合いが強いため謝礼金として扱われます。 - イベント協力や出演の謝礼
企業や地方自治体のイベントに参加し、協力したことに対するお礼。業務委託契約が存在しない場合には、報酬ではなく謝礼金として扱われます。 - アンケートや調査への協力に対する謝礼
消費者アンケートや市場調査などへの参加に対して、現金や商品券などが支払われる場合。 - 取材協力や執筆依頼の謝礼
メディアの取材に協力したり、記事の執筆に対して報酬ではなく謝礼が支払われるケース。
謝礼金は契約がないことが前提ですが、支払い金額が大きくなると「報酬」として扱われることがあります。また、継続的に同じ内容の謝礼金を受け取っている場合も「事業所得」や「給与」とみなされる可能性があるため、受け取る頻度や金額には注意が必要です。
報酬や給与との違い
謝礼金は、報酬や給与と混同されやすいですが、根本的に異なる点がいくつかあります。
| 項目 | 謝礼金 | 報酬 | 給与 |
|---|---|---|---|
| 契約の有無 | なし | あり | あり |
| 支払い義務 | 任意 | あり | あり |
| 支払い頻度 | 単発的 | 単発的 or 継続 | 継続的 |
| 源泉徴収 | 必要な場合あり | 必要 | 必要 |
| 社会保険・労働保険 | なし | 場合によりあり | あり |
| 消費税 | 基本的に非課税 | 課税対象 | 課税対象外(給与所得) |
報酬との違い
報酬は、役務提供の対価として支払われるものであり、法的に契約に基づいて支払い義務が生じます。一方、謝礼金は、契約義務のない「お礼」の性質が強いため、法的拘束力がない点が異なります。
給与との違い
給与は、雇用契約に基づき、労働の対価として定期的に支払われるものであり、所得税や住民税、社会保険料が控除されます。謝礼金は、雇用契約に基づかず単発的な支払いとなるため、給与とは区別されます。ただし、謝礼金が継続的に支払われる場合や、高額になる場合には、給与として扱われることがあります。
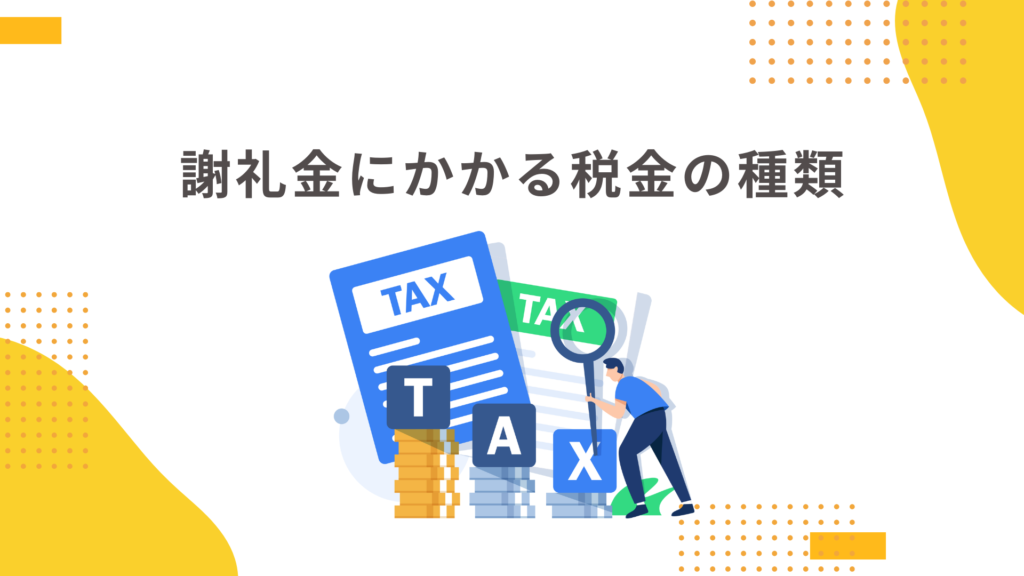
謝礼金にかかる税金の種類
謝礼金が課税対象になるケース
謝礼金は「所得」とみなされることが多いため、課税対象になるケースが多く存在します。謝礼金が課税対象になるかどうかは、以下のような要素が影響します。
1. 継続性がある場合
- 定期的に謝礼金を受け取っている
- 内容が同じで定期的に発生している
- 仕事や業務の一環として扱われている
例えば、毎月同じ企業から講演謝礼を受け取っている場合、謝礼金ではなく「報酬」や「給与」として扱われる可能性があります。
2. 対価性がある場合
- 労働や役務の提供がある
- 感謝の気持ちではなく、明確な報酬としての側面が強い
例えば、セミナーやイベントの講師として正式に依頼を受けた場合や、記事執筆を依頼された場合などは、「報酬」として源泉徴収が必要になるケースがあります。
3. 高額な場合
謝礼金の金額が高額になると、単なる「感謝の気持ち」ではなく、労働や報酬の側面が強くなると判断され、課税対象になる可能性があります。
源泉徴収義務の有無と税率
謝礼金が報酬に該当する場合、支払う側に「源泉徴収義務」が発生します。国税庁のガイドラインによれば、以下の税率が適用されます。
- 100万円以下の場合 → 10.21%(所得税 + 復興特別所得税)
- 100万円超の場合 → 20.42%(100万円を超える部分に適用)
例:講演料80万円の場合
- 80万円 × 10.21% = 81,680円 → 源泉徴収される金額
例:講演料150万円の場合
- 100万円 × 10.21% = 102,100円
- 50万円 × 20.42% = 102,100円
➡️ 合計:204,200円
源泉徴収された場合の注意点
- 源泉徴収されている場合でも、確定申告で過不足を調整する必要があります。
- 源泉徴収が過剰であれば還付を受けられる可能性があります。
100万円以下・100万円超で異なる税率
100万円を境に税率が異なるため、高額な謝礼金を受け取る場合には特に注意が必要です。
例1:講演料80万円の場合
- 80万円 × 10.21% = 81,680円
例2:講演料150万円の場合
- 100万円 × 10.21% = 102,100円
- 50万円 × 20.42% = 102,100円
➡️ 合計:204,200円
節税ポイント
- 経費を差し引くことで所得を圧縮できる
- 事業所得として計上すると税率を抑えることが可能
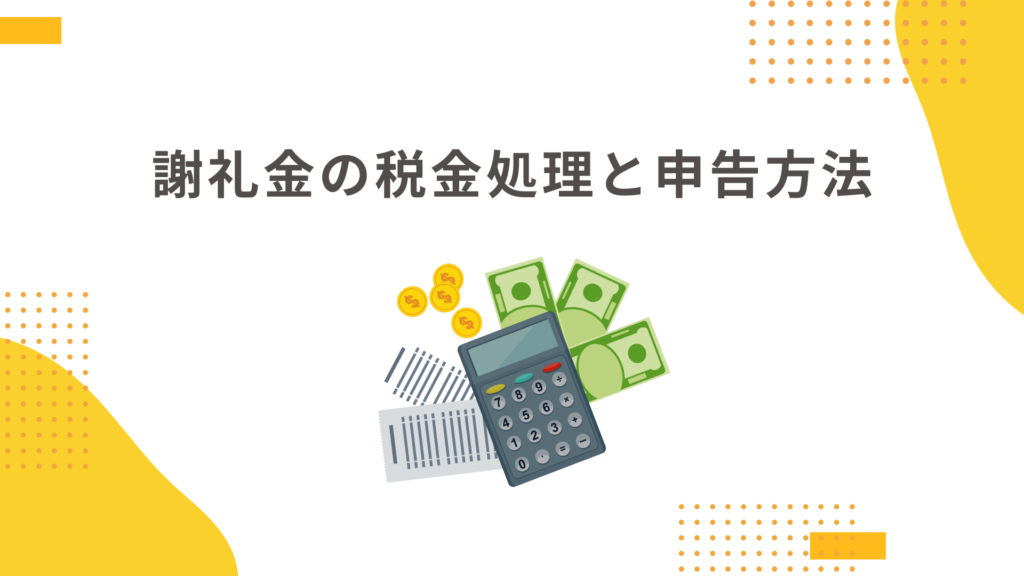
謝礼金の税金処理と申告方法
個人で受け取った場合の申告方法
個人が謝礼金を受け取った場合、所得税や住民税の対象になる可能性があります。謝礼金が労働や役務の提供に対する「報酬」に該当する場合や、一定の金額を超える場合には、確定申告を行う必要があります。
申告する際のポイント
- 雑所得として申告
- 謝礼金の受け取りが一時的で、継続的な収入ではない場合 → 雑所得として申告
- 必要経費(交通費や材料費など)を差し引いた金額が課税対象
- 事業所得として申告
- 謝礼金を継続的に受け取っている場合 → 事業所得として申告
- 収入から経費を差し引いて所得額を確定
- 源泉徴収がある場合の申告
- 源泉徴収がある場合 → 確定申告で過不足を調整
- 過剰に徴収されている場合 → 還付を受けられる可能性がある
雑所得としての記載例
確定申告書の「雑所得」欄に以下のように記載します:
| 区分 | 収入金額 | 必要経費 | 所得金額 |
|---|---|---|---|
| 謝礼金 | 100,000円 | 10,000円 | 90,000円 |
→ 所得金額90,000円に所得税が課税されます。
会社員が副業で受け取った場合の扱い
会社員が副業として謝礼金を受け取った場合も、税金の対象になります。
副業謝礼金の課税ポイント
- 年間の謝礼金が20万円以下の場合 → 所得税の確定申告は不要(ただし住民税の申告は必要)
- 年間の謝礼金が20万円を超える場合 → 所得税の確定申告が必要
副業の謝礼金が課税対象になるケース
- 企業から定期的に支払われる
- 対価性が明確にある(例:ライター報酬やセミナー講師料)
住民税への影響
- 確定申告をしなくても、給与以外の所得がある場合は「住民税申告」が必要
- 住民税申告を忘れると、後から住民税が増額される可能性がある
確定申告が必要になるケース
謝礼金に関して以下のケースに該当する場合は確定申告が必要です:
- 年間20万円を超える場合
- 副業や個人事業として受け取った謝礼金が年間20万円を超える場合
- 源泉徴収されていない場合
- 源泉徴収が行われていない謝礼金は、所得として自己申告が必要
- 事業所得として申告する場合
- 継続して謝礼金を受け取っている場合
- 住民税の申告が必要な場合
- 20万円以下でも住民税の申告義務がある

謝礼金に関する勘定科目の選び方
個人の場合:雑所得・事業所得の違い
謝礼金が雑所得か事業所得かを判断する基準は、以下のとおりです:
| 区分 | 説明 |
|---|---|
| 雑所得 | 単発的な謝礼や報酬 → 継続性がない |
| 事業所得 | 継続的に受け取る謝礼や報酬 → 事業的要素が強い |
- 雑所得 → 交通費や材料費などが経費として認められる
- 事業所得 → 事業運営に必要な経費(家賃や通信費など)も経費として認められる
法人の場合:交際費・手数料・広告宣伝費の分類
法人が支払う謝礼金の勘定科目は内容によって異なります。
| 内容 | 勘定科目 |
|---|---|
| 取引先や顧客への謝礼 | 交際費 |
| 講師料や取材協力費 | 支払手数料 |
| 商品モニターや広告協力謝礼 | 広告宣伝費 |
正しい仕訳と記帳方法
例:講師謝礼50,000円(消費税込み)を現金で支払った場合
- 借方:「支払手数料」50,000円
- 貸方:「現金」50,000円
例:広告協力に対する謝礼100,000円を銀行振込で支払った場合
- 借方:「広告宣伝費」100,000円
- 貸方:「普通預金」100,000円
謝礼金に消費税はかかる?ケース別に解説
謝礼金に消費税がかかるかどうかは、「対価性」があるかどうかが重要なポイントになります。対価性とは、金銭や物品が支払われる理由が「労働や役務の提供」に基づくものであるかどうかを指します。国税庁のガイドラインでは、謝礼金が報酬に該当する場合は消費税課税対象となると明記されていますが、単なる「お礼」としての性質が強い場合は消費税は非課税となります。
対価性がある場合の消費税課税条件
謝礼金に対価性があるとみなされるケースでは、消費税の課税対象になります。具体的には、以下のような場合に対価性があると判断されます:
- 講演料や講師謝礼
- 企業や団体から依頼されて講演を行い、その報酬として受け取った謝礼金
- 謝礼金を受け取るための労働や役務の提供が明確であるため、消費税の課税対象となる
- 原稿料・執筆料
- 企業や出版社から依頼されて記事や原稿を執筆し、謝礼を受け取るケース
- 原稿の執筆が「役務の提供」に該当するため、消費税が課税される
- 商品モニター謝礼
- 企業から商品のモニターを依頼され、その結果や感想を提供するケース
- 商品やサービスに関するフィードバックが「役務提供」に該当するため、消費税が課税対象
- イベント出演料
- 企業や団体のイベントに出演し、出演謝礼を受け取る場合
- 労働やサービスの対価とみなされるため、消費税が課税される
- 調査協力への謝礼
- 市場調査や消費者アンケートに協力し、その謝礼として支払われる場合
- 調査への協力が「役務の提供」に該当するため消費税が発生
【例】講演料10万円を受け取った場合
- 講演料:100,000円
- 消費税(10%):10,000円
➡️ 合計:110,000円
消費税が課税対象となる場合は、源泉徴収の計算とは別に消費税の処理を行う必要があります。
単なる「お礼」として扱われる場合の非課税条件
謝礼金が「対価性がない」と判断される場合、消費税の課税対象にはなりません。つまり、労働や役務の提供が伴わず、感謝や好意の気持ちとして支払われるケースです。具体的には以下のような場合に該当します
- ボランティアへの謝礼
- イベントや地域活動へのボランティア協力に対して渡される謝礼金
- 労働や役務の提供を目的としていないため非課税
- アンケート回答への謝礼(抽選や景品の場合)
- アンケート回答に対して、金銭や物品が「お礼」として渡される場合
- 役務提供ではなく感謝の気持ちに基づくものとみなされ、非課税となる
- 贈与的な謝礼
- 労働や役務の提供の見返りではなく、純粋な贈与としての謝礼金
- 税務上は「贈与」として扱われ、消費税は非課税となる
- 感謝の気持ちに基づく一時的な謝礼
- 例えば、イベントの参加者に対して感謝の意味で現金や商品券を配布する場合
【例】イベントの参加謝礼3,000円を受け取った場合
- 単なる感謝の意 → 非課税
➡️ 確定申告時も「消費税なし」として処理可能

謝礼金の領収書・記録の扱い方
領収書が必要になるケース
謝礼金を受け取った場合や支払った場合、領収書が必要になるケースがあります。以下のような場合には、必ず領収書を受け取るようにしましょう。
- 経費として計上する場合
- 受け取った謝礼金を「事業所得」や「雑所得」として申告する場合
- 謝礼金を支払った側が経費として処理する場合
- 源泉徴収が発生した場合
- 謝礼金から源泉徴収が行われた場合は「支払調書」が必要
- 支払調書が発行されない場合は領収書で代用可能
- 税務署から提出を求められる可能性がある場合
- 確定申告や税務調査で証拠として提出が必要
領収書がない場合の記録方法
領収書を受け取ることができなかった場合でも、以下のような記録を残しておくことで証拠として認められる可能性があります。
- 振込記録や通帳のコピー
- 銀行振込やクレジットカード決済などの明細
- 金額や支払い先、日付が確認できるもの
- メールや契約書
- 依頼内容や金額が記載されたメール
- 依頼時の契約書
- レシート・支払明細書
- 領収書に代わるものとして税務上認められるケースあり
- メモ・記録書
- 支払い内容や受け取った金額、日付、相手方を記録したメモ
税務調査時に求められる証拠の準備
税務調査では、謝礼金に関する支払いや受領の記録が確認されることがあります。以下のような証拠を準備しておくことでスムーズに対応可能です。
- 領収書・支払調書
- 謝礼金に関する正式な証拠
- 契約書・メールのやり取り
- 謝礼金の支払いに関する合意内容
- 通帳のコピー・振込記録
- 実際の支払い記録
- 仕訳帳・帳簿
- 謝礼金の仕訳内容が確認できるもの
税務調査時に不備があると、過少申告加算税や延滞税が課される可能性があります。早めに記録を整備しておくことが重要です。
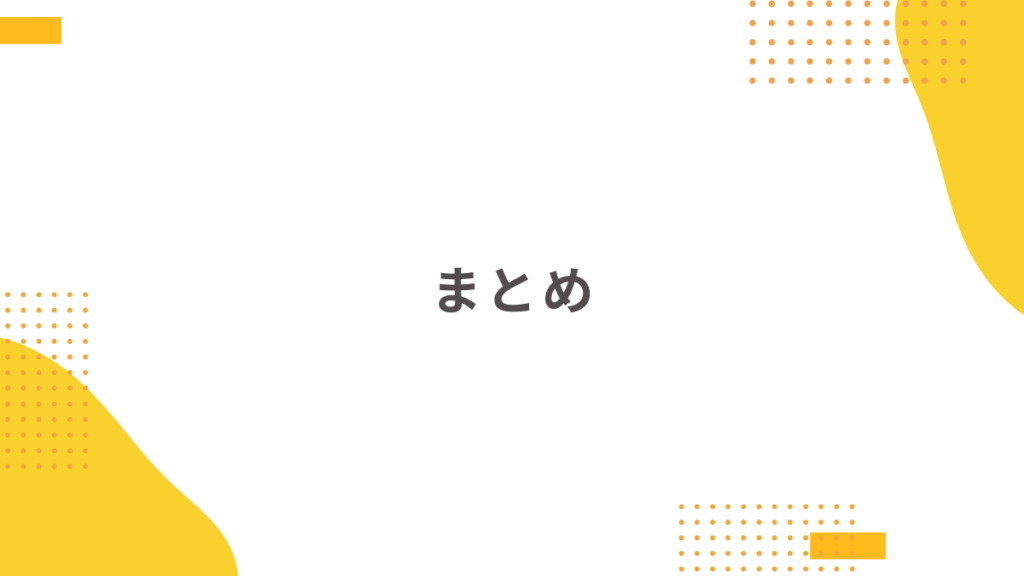
まとめ
謝礼金は、講演やイベントの出演、アンケート協力、原稿執筆など、労働や役務の提供に対する「報酬」的な側面を持つ場合と、単なる「お礼」として支払われる場合があります。謝礼金が報酬に該当すると、所得税や住民税の課税対象となるため、適切な税務処理が求められます。また、消費税に関しても「対価性」があるかどうかで課税・非課税が判断されるため、性質を正確に理解することが重要です。
税務処理においては、受け取った謝礼金が「雑所得」なのか「事業所得」なのかを見極め、正しい勘定科目で仕訳・記帳を行う必要があります。さらに、法人が謝礼金を支払う場合には、交際費や支払手数料、広告宣伝費などの勘定科目を正しく分類し、消費税の扱いを含めて正確に処理することが求められます。
また、税務調査や確定申告に備えて、謝礼金の受け渡しに関する領収書や振込記録、契約書などを適切に保存しておくことが重要です。領収書がない場合でも、振込記録やメールなどが証拠として認められるケースがあります。
本記事を参考にして、謝礼金の正しい税務処理や申告方法を理解し、トラブルを避けるための準備をしておきましょう。謝礼金を適切に管理・申告することで、節税効果が得られる場合もあります。知識を身につけて、安心して謝礼金を受け取れるようにしましょう。
