ギフトカード・商品券の郵送方法とは?安全発送の選び方と補償・梱包を徹底解説
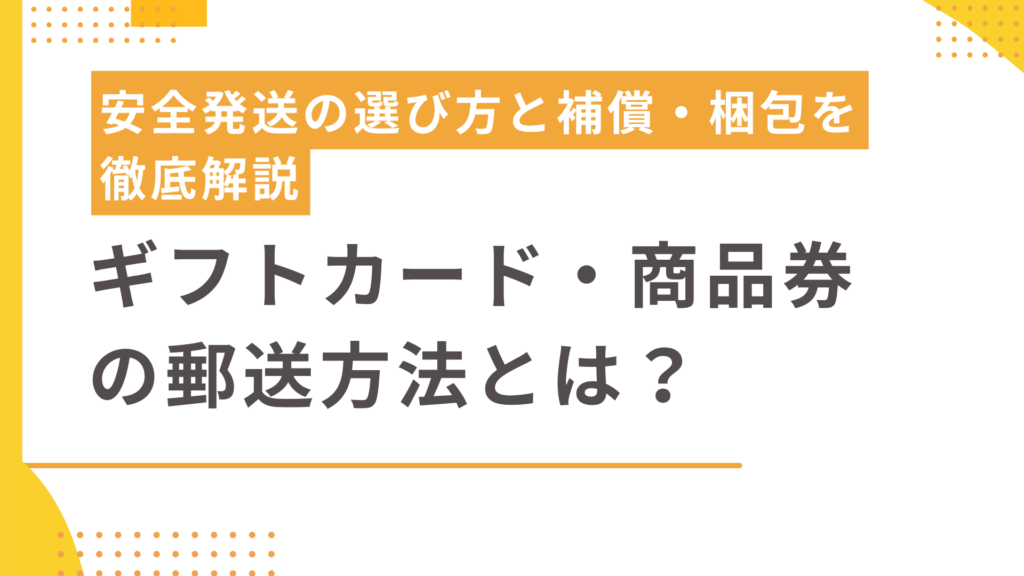
大切な方へ贈るギフトカードや商品券。大切だからこそ、郵送時にも「安全かつ丁寧に届けたい」ものですよね。本記事では、法律的な扱いから信頼できる発送方法、補償つきの梱包術まで、多角的に徹底解説します。郵便局の公式見解や補償制度に基づく信頼性の高い情報を交え、失敗のない発送ガイドをご提供します。
ギフトカードは郵送できる?法律上の取り扱い

ギフトカードや商品券は、総務省・日本郵便によって「信書に該当しないプリペイドカード類」と明確にされています。これは法律上、郵送に関する制限がないことを意味します(つまり自由に送付可能)。とはいえ、有価物としての扱いであり、誤配や盗難リスクを考えると、追跡・補償付きの方法を選ぶのが賢明です。加えて、マナーや相手への配慮も大切。公式見解に基づいて適切な発送準備をすることで「安全に・丁寧に」届けられる体制が整います。
ギフトカードや商品券は信書にあたる?
「信書」とは特定の相手へ意志を伝える文書を指しますが、ギフトカードや商品券は含まれません。このため、実務上も安心して郵送できます。誤解を招きやすい現金書留とは異なり、カード単独での送付は規制対象外です。ただし、送り方によっては取り扱い注意となる場合もあるため、送る側が制度を正しく理解した上で選ぶことが重要です。
日本郵便が認めている発送方法と理由
日本郵便は安全配達のために、簡易書留・一般書留・ゆうパック・レターパックなどを推奨しています。それぞれに「追跡」「補償」の機能があり、有価物送付のリスク軽減につながります。例えば書留は持ち出しから配達まで記録され、万一の場合には補償対象(簡易=5万円、一般=10万円以上)があり、さらにゆうパックにセキュリティオプションを追加することで補償額を50万円まで引き上げることも可能です。
商品券の安全な発送方法一覧と選び方
発送方法は大きく「簡易書留」、「一般書留」、「レターパック(ライト/プラス)」、「ゆうパック」に分けられます。送る目的(金額・枚数・重量)に応じて選ぶことで安心度とコストのバランスが取れます。補償が必要ない場合はレターパックが手軽ですが、価値がある商品券には補償付きの書留かゆうパックを選ぶのがベストです。店舗発送代行サービスを利用すれば、梱包~発送まで一括で準備でき、贈り物としての完成度も上がります。
簡易書留・一般書留の特徴と補償範囲
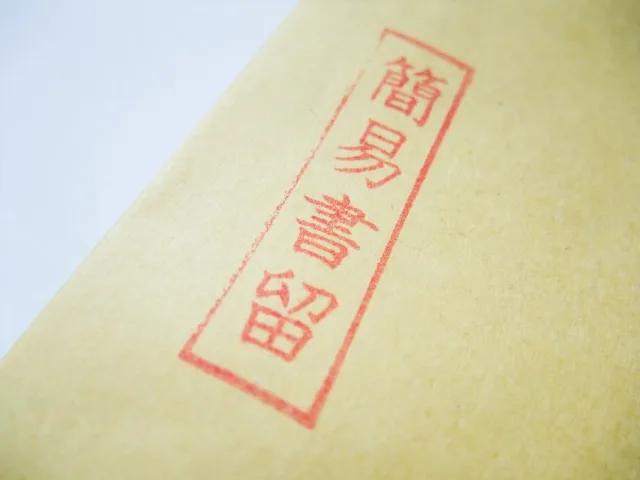
簡易書留は基本郵送料に+350円、追跡・記録と最大5万円の補償が付与されます。価格が手ごろで、小額カードの送付に向いています。
一般書留は+480円、最大10万円まで補償され、さらに5万円ごとに23円追加で最大500万円まで増額可能です。高額商品券やまとめ送付時にはこちらが適切です。
両者とも追跡記録が残るため、万一の場合でも履歴確認ができ、信頼性が高い発送方法です。
レターパックライト/プラスの違いと注意点


レターパックライト(430円)は郵便受けへの投函で送付でき、厚さ3cm以内・A4サイズ・4kgまで。一方、レターパックプラス(600円)は対面手渡しで配達されますが、どちらも補償はありません。しかし追跡番号により配送状況の確認は可能です。手軽でスピーディですが、失敗を避けたい高額カードには不十分です。
ゆうパックで送る場合のポイント

ゆうパックは追跡・補償(最大30万円)付きで、重さと距離により料金が変動します。
さらにセキュリティオプション(+420円)を付けると補償上限が50万円にアップします。数量が多いセット商品や高額カードを送る際に、ゆうパックは非常に有用です。また品名欄には「商品券○枚」など明記し、中身が特定できるようにすると紛失時に手続きがスムーズになります。
民間宅配は使える?ヤマト・佐川NGの理由

ヤマト運輸や佐川急便などは、有価証券(商品券・ギフトカード等)の扱いを禁止しています。これは各社の利用規約に明記されており、日本郵便以外では対応できません。規約違反の場合、事故時に補償が受けられないばかりか、荷物自体を拒否される可能性もあります。代替としては専門の貴重品輸送業者を使う方法がありますが、コストが高く業務利用向けです。
送ってはいけない発送方法とその理由
普通郵便・定形外・ゆうメールは追跡も補償もなく、盗難・紛失時のリスクが非常に高いため、有価物送付には不適当です。
現金書留は名称に「現金」とありますが、商品券単体では利用できず、誤って使用すると返送や手続き上のトラブルになる場合もあります。
高額送付時や大切な贈り物であれば、必ず補償付きの適切な方法を選びましょう。
普通郵便や定形外が避けられる理由
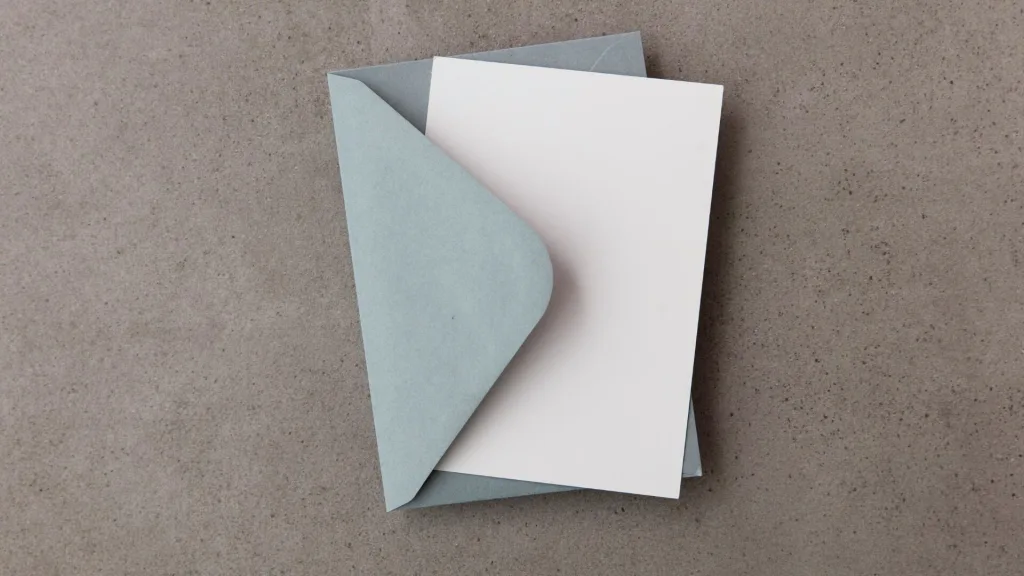
これらの郵送方法は「最低限の手段」として存在し、追跡・補償機能が全く付かないため、送付中の事故・紛失に対応できません。
郵便局の損害賠償制度においても、「書留やオプション付きサービス以外は対象外」と明記されています。万一のトラブルが起こると、再発行や損害補償ができず、贈り主・受け手双方にとって大きな負担となるため、避けるべき方法です。
現金書留と金券の誤解
現金書留は文字通り「現金専用」です。商品券やギフトカード単体で申請すると拒否されます。ただし、封筒に現金と一緒に同包する場合、「現金書留」としての補償対象になり、合計金額分が補償されます。サービス利用時は「現金封筒」を使い、申請時に窓口で正確に金額申告をしましょう。
ギフトカードが盗難・紛失されたらどうなる?
万一盗難や紛失が発生しても、選んだ発送方法に応じて補償が支払われます。簡易書留は5万円まで、一般書留は10万円〜最大500万円(拡張オプションあり)、ゆうパックは30万円〜50万円。ただし、補償の対象になるためには「追跡番号保存」「事故申請」「補償申請書提出」など正しい手続きを行うことが必要です。不安がある場合は、発送後の連絡を受取人にしておくのも有効です。
プロが教える!梱包のコツとおすすめ資材

商品券やギフトカードを送る際、輸送中の「水濡れ」「折れ」「紛失」を防ぐ梱包は非常に重要です。とくに個人で発送する場合、封筒にそのまま入れるのは危険。郵便事故やトラブルを未然に防ぐため、適切な資材と方法を使って梱包しましょう。市販のアイテムや100円ショップでも入手できる便利グッズを活用することで、コストを抑えながら安全性を確保できます。以下で詳しく説明します。
水濡れ防止(OPP袋・ジップバッグ)

雨や湿気などによる水濡れから商品券を守るには、OPP袋やジップ付きポリ袋が効果的です。これらは中身を密閉することで水の侵入を防ぎ、印刷のにじみや破損を避けられます。特にOPP袋は透明で封筒内の視認性も保てるため、郵便局員にも中身が分かりやすく好印象です。ジップバッグは厚みがあるため、しっかり密封できる反面、封筒サイズに収まるよう注意が必要です。どちらも防水対策としては必須のアイテムといえます。
折れ・破損対策(厚紙・クッション封筒)
輸送中の折れ曲がりや破損を防ぐためには、厚紙やクッション封筒を使った二重保護が推奨されます。商品券の両面に厚紙を挟んで封筒に入れることで、圧力や折れに対する耐久性が向上します。クッション封筒(プチプチ付き封筒)は衝撃吸収にも優れており、高価なギフトカードや複数枚送る場合に安心です。文房具店や100均ショップでも購入可能で、梱包資材に迷った際はまず取り入れたいアイテムです。
封筒サイズ・ラベルの記載方法
封筒はA5〜長3(23.5×12cm)サイズが標準で、商品券が余裕をもって入るものを選びましょう。サイズが合わないと封筒が膨らみ、機械仕分けで損傷するリスクがあります。宛名は丁寧に楷書で記載し、「○○様ご在宅」「折曲厳禁」などの注意ラベルを添えると、配達員への配慮が伝わり、信頼感もアップします。また、裏面に差出人住所と連絡先も明記しておくと、トラブル時に返送・連絡がスムーズです。
発送時の料金と補償額の比較一覧

発送方法を選ぶ上で重要なのが、コストと補償のバランスです。追跡や補償の有無により、同じような料金でもサービス内容が大きく異なります。以下の早見表を参考に、商品券の金額・数量・重要度に応じて最適な方法を選びましょう。また、高額な商品券を送る際には補償の上限額も確認が必要です。必要に応じてオプションを追加することで、万が一の事態にも備えられます。
各発送方法の料金と補償内容早見表
「どの発送方法が自分に最適か?」がひと目で分かるよう、料金・補償・特徴をまとめました。大切なのは“何をどれだけ送るか”に応じた発送方法の選択です。
| 発送方法 | 追加料金 | 補償額 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 簡易書留 | +350円 | 最大5万円 | 追跡・補償あり。小額用。 |
| 一般書留 | +480円〜 | 最大500万円 | 高額対応。補償額の拡張可能。 |
| レターパックライト | 430円 | 補償なし | 郵便受け投函。軽量・簡易送付向け。 |
| レターパックプラス | 600円 | 補償なし | 対面配達。補償不要なケースに便利。 |
| ゆうパック | 距離・サイズによる(例:820円〜) | 最大50万円 | 重量物や大量送付に最適。 |
追加補償が必要なケースと申し込み方
高額な商品券や複数枚をまとめて送る場合は、一般書留の補償拡張やゆうパックのセキュリティオプションの利用を検討しましょう。一般書留は5万円を超えるごとに+23円で補償額を増やせ、最大500万円まで対応可能です。ゆうパックのセキュリティサービスは+420円で最大50万円まで補償され、受取人確認などのセキュリティ対策も強化されます。申込は郵便窓口で簡単に行えるため、重要書類や有価物には積極的に利用するのがおすすめです。
よくある質問(FAQ)

商品券と現金を一緒に送っても大丈夫?
はい、商品券と現金を一緒に送ることは可能ですが、その場合は必ず「現金書留」を使ってください。通常の書留やレターパックでは現金を送ることは認められていません。現金書留であれば、中に入れた商品券も含めた合計金額に応じて補償が適用されます。ただし、封筒は専用の「現金書留封筒」を使用し、差出時に内容金額を申告する必要があります。受取人が不在の場合には手渡しのため、確実に届きます。
相手が受け取れなかったときはどうなる?
書留やゆうパックで送付した場合、相手が不在であれば不在票が投函され、再配達を依頼することができます。また、郵便局に一時保管される期間もあり、その間に受取人から連絡がない場合には差出人へ返送されます。レターパックプラスも同様に対面配達のため、不在時は持ち帰り対応となります。再配達や保管期限などの情報は追跡番号で確認できるため、差出人が状況を把握しやすいのも安心材料です。
郵便事故時の補償手続きの流れは?
郵便事故が発生した場合、まずは追跡番号をもとに配達状況を確認します。もし紛失や破損が確認された場合は、郵便局で事故申告を行い、「損害賠償申請書」を提出します。簡易書留や一般書留、ゆうパックなど補償対象の発送方法であれば、補償額内で賠償金が支払われます。申請には受領証や内容証明などの提出が求められるため、発送時の控えは必ず保管しておきましょう。補償には一定期間がかかることもありますが、正しい手続きを踏めばしっかり対応してもらえます。
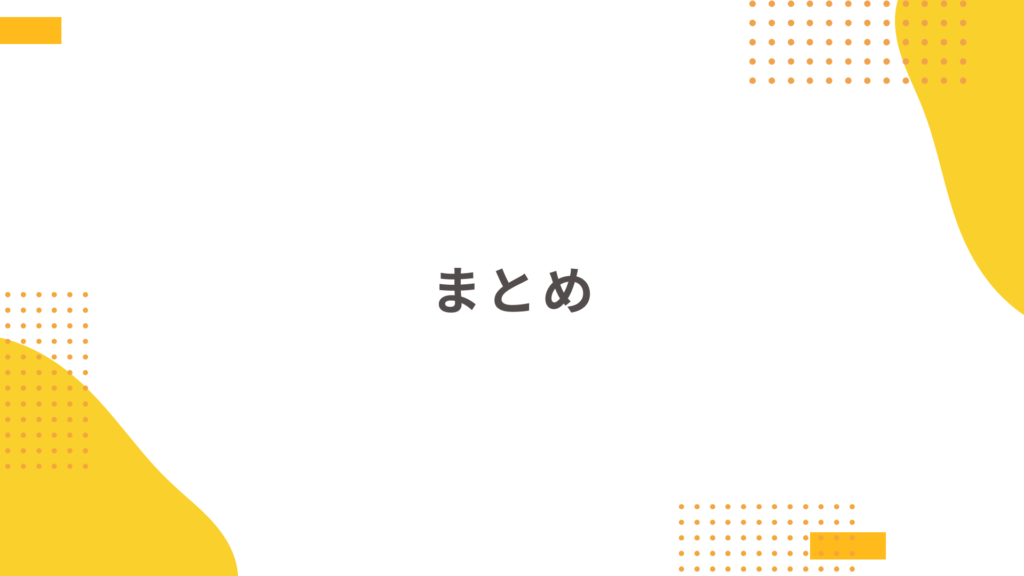
まとめ
ギフトカードや商品券を郵送する際、最も大切なのは「確実に・安全に・丁寧に届ける」ことです。信書に該当しないため郵送は可能ですが、有価物である以上、発送手段・補償内容・梱包方法にこだわることで受け取り手の満足度や信頼感が大きく変わります。この記事でご紹介した内容は、個人の贈り物から法人のギフト発送まで幅広く応用可能です。悩んだときはこの記事を再確認して、最善の発送方法を選びましょう。
