【例文あり】ビジネスでも使える6月の時候の挨拶

時候の挨拶とは、日本の手紙文化において季節の移り変わりを言葉で表す冒頭の決まり文句です。特に梅雨入りを迎える6月は、体調や天候に配慮した表現が好まれ、受け手への気遣いや心遣いが伝わります。
本記事では、6月の時候の挨拶の例文やポイントなどを解説します。
6月の時候の挨拶とは?
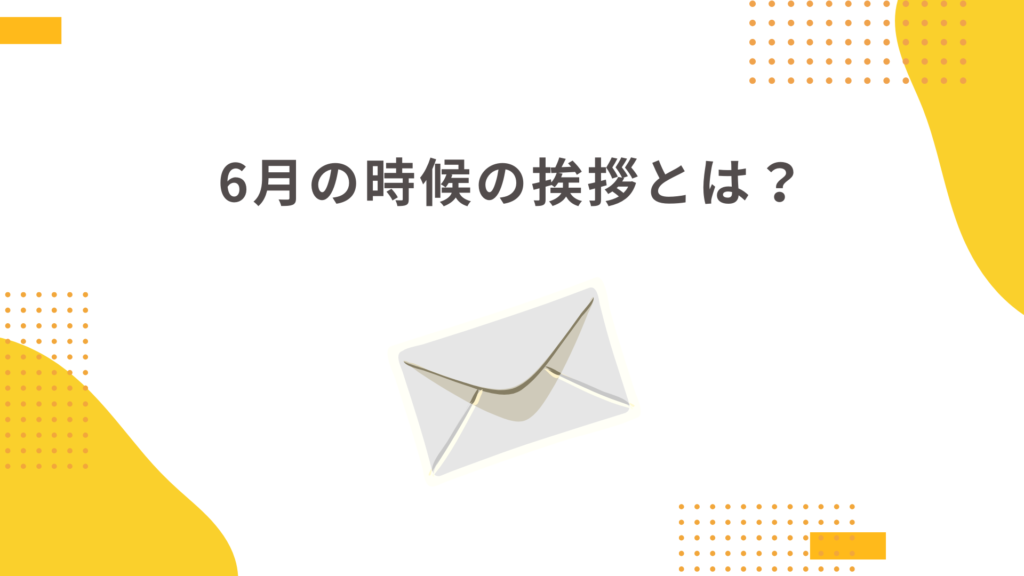
6月の特徴と季節感
6月は一年の中でも特に季節の変わり目を感じやすい月です。「梅雨」という独特の気象現象と、「初夏」から「盛夏」へと移行する過程が重なることで、手紙や挨拶文にも湿潤な空気感や瑞々しさを表現する語彙が数多く使われます。
◆ 気候:梅雨と初夏の共存
6月の代表的な気象といえば梅雨(つゆ)です。日本列島の広い範囲で梅雨入りが発表される時期であり、長くしとしとと降る雨、曇り空、湿度の高さなどが続きます。
この時期に使われる時候の言葉には以下のようなものがあります:
- 「入梅の候」
- 「長雨の候」
- 「梅雨の候」
- 「向暑の候」(=夏の暑さに向かう意味)
一方で、6月は夏至も迎えるため、昼が最も長くなり、暦の上では初夏の終わりから本格的な夏の始まりとなります。この季節感を「向暑」「薄暑」「初夏」などの表現で捉えることができます。
◆ 自然:植物・動物が豊かに
6月は自然の変化が鮮やかで、手紙に取り入れやすい季節です。
- 紫陽花(あじさい):梅雨の代名詞とも言える花で、「移ろいやすい美しさ」「日本的情緒」を表現するのに最適。
- 花菖蒲(はなしょうぶ)・杜若(かきつばた):水辺の美しい花として6月の代表。
- 青葉・若葉・深緑:新緑から深みを増す葉の色合いも季節感を強調するポイント。
- カタツムリ・カエル:雨とともに思い出される生き物で、親しみやすい印象を与える。
◆ 行事・歳時記との関わり
6月は年間行事が少ないと思われがちですが、実は日本文化と密接に関係する行事があります。
- 衣替え(6月1日):制服やスーツが夏仕様になる節目。季節の区切りを意識させるきっかけに。
- 父の日(6月第3日曜日):感謝を伝える挨拶や贈り物と合わせて使用可能。
- 夏至(6月21日頃):一年で最も日照時間が長く、太陽の力強さを感じさせる表現に。
- 夏越の祓(6月30日):半年の穢れを祓う神事。文面に入れると風流な印象を与えられる。
◆ 食文化や風物詩
食べ物や風物詩も6月らしさを伝える大切な要素です。
- ところてん・冷やしそうめん・新茶・梅酒など、爽やかで涼感を与える食材が季節を彩ります。
- 水無月(和菓子)は旧暦6月にちなんだ菓子で、厄除けの意味があり、季語としても使用可能です。
6月の時候の挨拶(上旬・中旬・下旬)
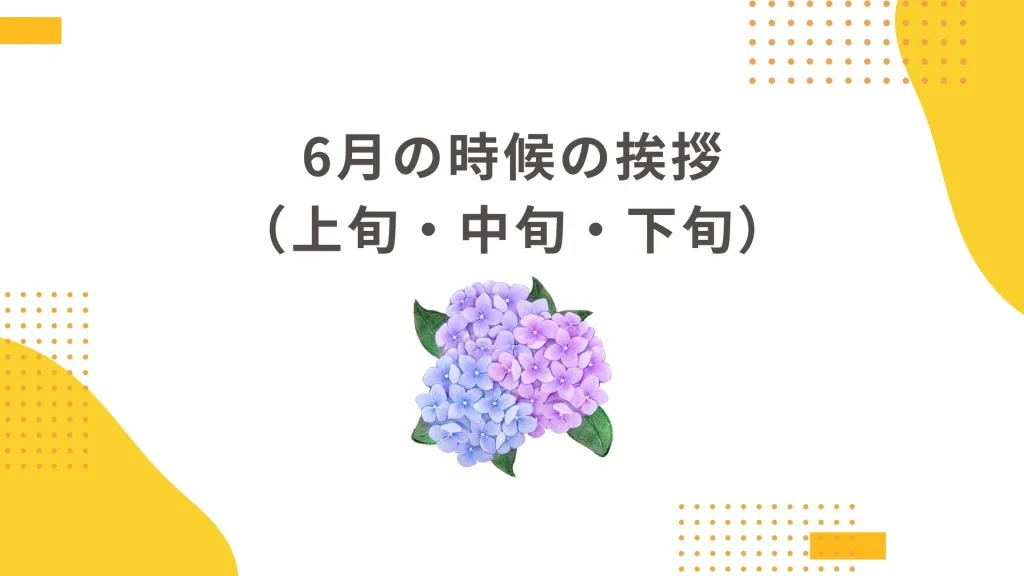
6月上旬の挨拶例
6月上旬は、まだ梅雨入りしていない地域も多く、初夏の爽やかさを表現するのが一般的です。
ビジネス向け
- 「初夏の候、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。」
- 「向暑のみぎり、皆様には益々ご清祥のことと拝察いたします。」
私用・カジュアル
- 「新緑がまぶしい季節となりましたね。お元気ですか?」
- 「そろそろ梅雨入りの気配が感じられるこの頃、いかがお過ごしでしょうか。」
6月中旬の挨拶例
梅雨の気配が色濃くなり、しっとりとした表現が中心になります。
ビジネス向け
- 「梅雨の候、貴社ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。」
- 「長雨の候、社員皆様におかれましてはご健勝のことと存じます。」
私用・カジュアル
- 「雨に濡れた紫陽花がきれいですね。お変わりありませんか?」
- 「梅雨の晴れ間に夏の気配を感じる今日この頃、元気にされていますか?」
6月下旬の挨拶例
梅雨も終盤に差しかかり、蒸し暑さや夏の到来を感じさせる表現が用いられます。
ビジネス向け
- 「向暑の候、貴社ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。」
- 「暑さ厳しき折、皆様におかれましてはご自愛専一にてお過ごしください。」
私用・カジュアル
- 「いよいよ夏本番が近づいてまいりましたね。」
- 「暑さが日に日に増してまいりましたが、いかがお過ごしでしょうか?」
ビジネスシーンでの6月の時候の挨拶
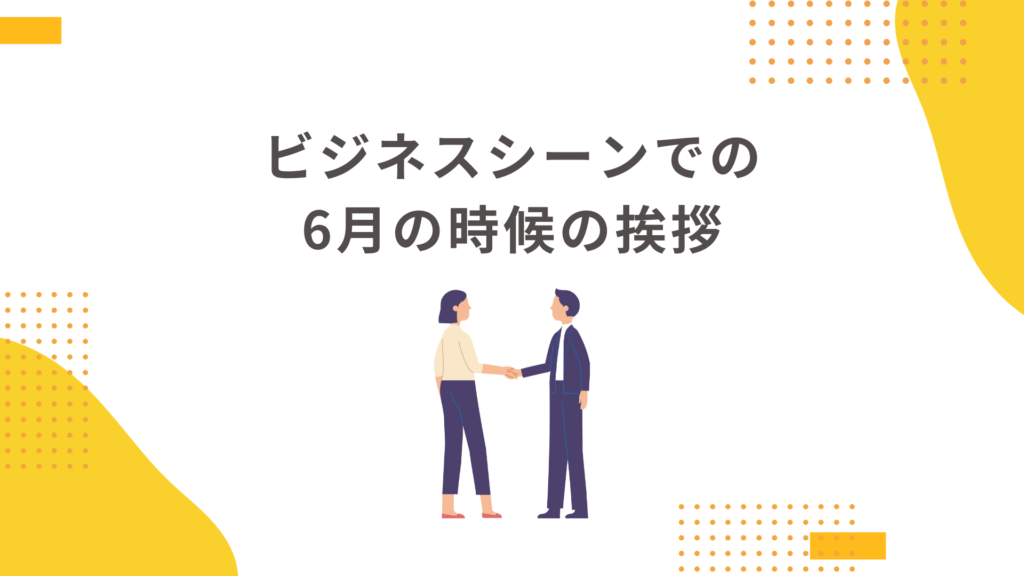
漢語調の表現と例文
漢語調とは、「○○の候」「○○のみぎり」といったフォーマルな表現方法で、改まった文書に適しています。
よく使われる漢語調表現:
- 向暑の候
- 梅雨の候
- 入梅の候
- 長雨の候
使用例:
向暑の候、貴社いよいよご清栄のこととお慶び申し上げます。
日頃は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
送付状や履歴書での使い方
送付状例
入梅の候、貴社ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。
さて、下記の書類を送付させていただきますので、ご査収の程お願い申し上げます。
履歴書添え状例
梅雨空が続くこの頃、貴社ますますご発展のこととお慶び申し上げます。
このたびは貴重な機会を賜り、誠にありがとうございます。
下記に必要書類を同封いたしましたので、ご確認のほどよろしくお願いいたします。
プライベートでの6月の時候の挨拶
口語調・和語調の表現と例文
口語調や和語調は、温かみがあり、親しみやすい印象を与えます。友人や家族、親しい取引先におすすめです。
例文
- 「じめじめした日が続いていますが、体調など崩されていませんか?」
- 「紫陽花が見ごろを迎えていますね。あなたの街でも咲いていますか?」
親しい人への手紙での使い方
手紙例
梅雨入りしてから、傘が手放せない日が続いていますね。
お元気にされていますか?
紫陽花を見るたびに、去年一緒に行ったあの公園を思い出します。
体調を崩しやすい時期なので、どうかご自愛ください。
6月の結びの挨拶の例
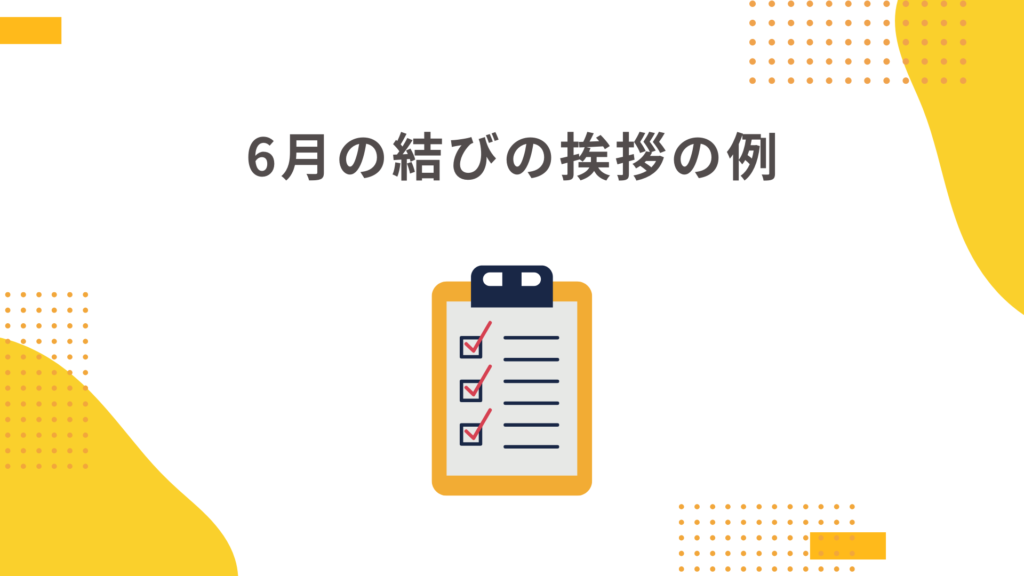
時候の挨拶と同様に、結びの挨拶は手紙やメールの印象を左右する大切な要素です。6月は気候が不安定で体調を崩しやすいため、相手を気遣う言葉や健康を祈る表現が好まれます。
ビジネス向けの結びの挨拶
ビジネスでは、礼儀正しさ・誠実さ・今後の関係性を意識した文が基本です。6月特有の気候や状況に配慮した表現を用いると、信頼感や好印象に繋がります。
定番の表現例:
- 「梅雨寒の折、くれぐれもご自愛のほどお願い申し上げます。」
- 「貴社の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。」
- 「何卒ご健勝にてお過ごしくださいますようお願い申し上げます。」
- 「蒸し暑い日が続きますが、皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。」
使用シーン例:
【営業メール】
今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
梅雨寒の折、どうぞご自愛くださいませ。
【請求書・見積書添付時】
ご査収のほどお願い申し上げます。
今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
カジュアルな結びの挨拶
プライベートな手紙や親しい相手とのやりとりでは、形式にこだわらず、温かく自然な言葉選びが好印象です。季節の話題と健康への気遣いをさりげなく盛り込むのがポイントです。
カジュアルな例文:
- 「梅雨の晴れ間が待ち遠しいですね。どうかお体に気をつけて。」
- 「雨が続きますが、心は晴れやかに過ごしていきたいですね。」
- 「紫陽花のように鮮やかな6月になりますように。」
- 「体調を崩しやすい時期ですので、無理せず過ごしてくださいね。」
親しい友人への使用例:
雨続きで洗濯物が乾かなくて大変だけど、なんだかんだで6月は好きです。
風邪などひかないように気をつけて。では、また連絡します!
祖父母や目上の親族宛て:
季節の変わり目ですので、お体を大切にお過ごしください。
近いうちにまたお顔を見せに行きますね。
6月の季節感を伝えるキーワード
挨拶文や手紙に6月ならではのキーワードを自然に盛り込むことで、豊かな季節感と情緒を表現できます。以下では、ジャンル別に代表的なキーワードとその表現例をご紹介します。
行事・イベント
6月には意外と多くの伝統行事や季節の節目があります。これらを文中に加えることで、文化的な奥行きや話題性を高められます。
- 衣替え(6月1日)
例:「衣替えの季節、心も装いも新たに前向きな気持ちになりますね。」 - 父の日(第3日曜日)
例:「父の日が近づいてきました。プレゼント選びに迷う季節です。」 - 夏至(6月21日頃)
例:「夏至を迎え、陽射しの強さに本格的な夏の訪れを感じます。」 - 夏越の祓(6月30日)
例:「夏越の祓にて半年の厄を祓い、無病息災を願う季節ですね。」
花・植物・生き物
6月は植物が生き生きと輝く季節。自然や花の描写は、情緒あふれる表現として定番です。
- 紫陽花(あじさい)
例:「紫陽花の色づきが日に日に濃くなり、散歩が楽しみな季節です。」 - 菖蒲(しょうぶ)・杜若(かきつばた)
例:「雨に濡れる菖蒲の花が、庭先を彩っています。」 - 若葉・青葉・深緑
例:「深緑のまぶしい季節となりました。」 - カタツムリ・カエル
例:「庭先でカタツムリを見つけて、子どもの頃を思い出しました。」
天候・暦
6月の天候は「不安定さ」「湿度の高さ」「晴れ間のありがたさ」などがキーワードです。手紙においては天候をクッションにして本文へ移行することが多いため、豊富な語彙を覚えておくと便利です。
- 長雨・梅雨前線・梅雨寒・梅雨の晴れ間
例:「梅雨の晴れ間に感じる陽射しの温かさが、ありがたく思える毎日です。」 - 水無月(旧暦の呼び名)
例:「水無月とはいえ、実際は雨が続きますね。」 - 蒸し暑さ・湿気・じめじめ
例:「蒸し暑さに負けず、しっかり食べて元気に過ごしたいものです。」
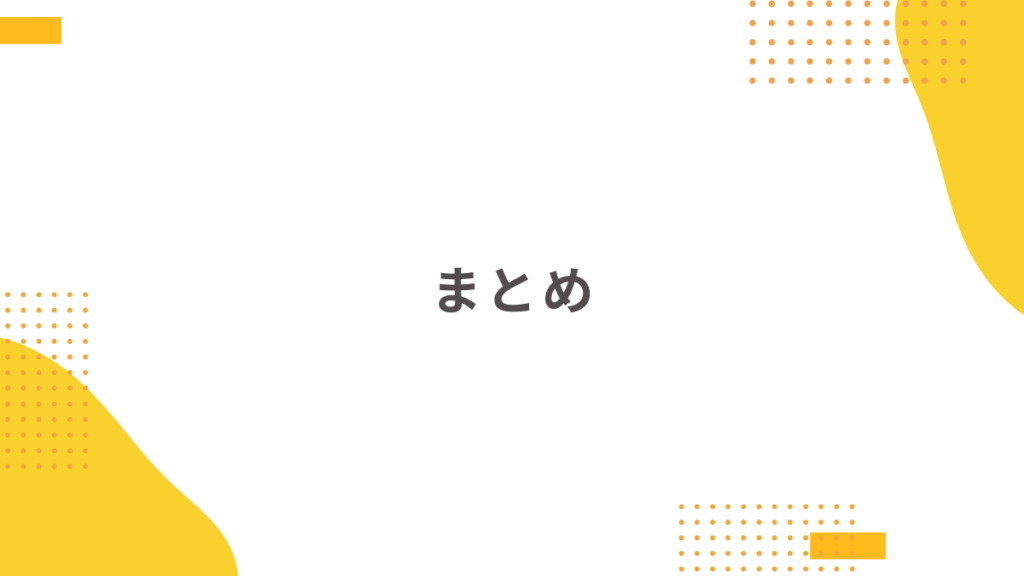
まとめ
6月は、気候的には過ごしづらさもある一方で、豊かな自然・文化・行事が凝縮された季節です。
挨拶文や手紙では、これらの特徴を的確に捉えた表現を用いることで、単なる形式ではない、“心を伝える文章”として相手の印象に残るものになります。
時候の挨拶と結びの言葉をセットで意識することで、文章の完成度が格段に上がります。ぜひ、この記事を参考に、6月らしい挨拶文を自分の言葉でつづってみてください。
